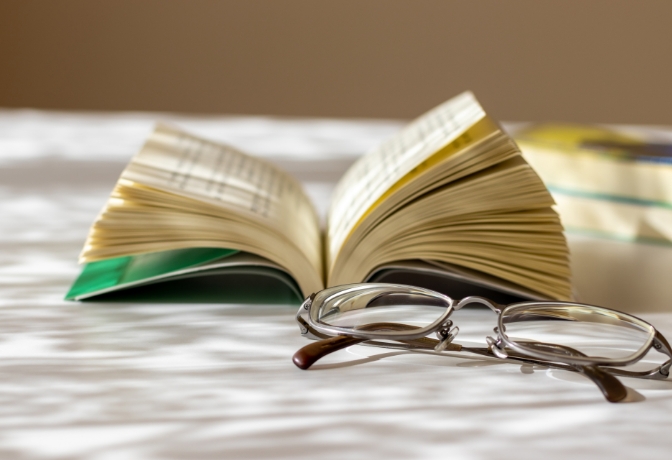『同朋』11月号対談を特別公開します
掲載日:2023/12/22 18:18
カテゴリー:メイン
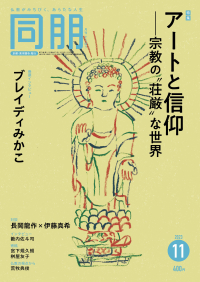
『同朋』11月号のご購入はこちら
日本美術史の重要なテーマの一つでもある仏像。そこからから見えてくるアートと信仰の関係性とは。
日本美術史の視点から仏像を研究し続けてきた長岡龍作さんと、
イラストレーターや消しゴムはんこ作家としても活躍する伊藤真希さんの対談です。
家族旅行はいつも奈良のお寺
伊藤 私は滋賀県長浜市の寺に生まれ、昨年から住職を務めています。琵琶湖の湖北にあたる場所で、真宗大国といわれるほど浄土真宗のお寺が多い場所です。また、消しゴムはんこ作家としても活動しておりまして、この月刊誌『同朋』では昨年まで表紙を担当させてもらいました。門徒さんに向けて、仏さまをモチーフにした作品を作ったこともあり、このたびは仏像のお話などをお聞きしたいと楽しみにして参りました。よろしくお願いいたします。
長岡 こちらこそよろしくお願いします。伊藤さんがお住まいの地域は、真宗寺院も多いですが、歴史ある観音菩薩像が安置されてる寺院もたくさんありますね。
伊藤 はい。近年は「観音の里」と呼ばれて、全国各地から多くの方々が参拝に訪れています。ただ、私にとっての仏像との出会いというと、やはり生まれたお寺の本堂に安置されている阿弥陀如来像です。生まれてからずっと、手を合わせてきた、共に暮らしてきたという感覚です。
前住職の父は高校で日本史の先生をしていたこともあってか、仏像に大変関心を持っていたので、家族旅行というと、必ずといっていいほど奈良のお寺でした。いろんなお寺の廊下や山門で撮った家族写真がたくさん残っています。いま思えば貴重な経験だったかもしれませんが、正直なところまだ幼なかった当時の私にとっては全然面白くありませんでした(笑)。それでも記憶に残っているのは、母が「この優しい顔はどう思う?」とか「しなやかな体がきれいやね」と、仏さまの姿やお顔について、子どもにもわかりやすいように話をしてくれたことですね。
今回、先生のご著書『日本の仏像』(中公新書)を読ませていただいたのですが、紹介されているお寺にあの頃お参りしていたなと懐かしく思い返しつつも、それぞれの仏像の願いや背景を知って、改めてお参りしてみたいなと思いました。
長岡 お読みいただきありがとうございます。私は、子ども時代は北海道で育ちました。私の地元も真宗寺院がたくさんある地域ですが、古い仏像はありませんでしたので、関西の古い寺院や仏像に、遠い土地から憧れるような仏像少年でした。
フェノロサから始まった仏像の「アート的」な見方
長岡 初めて憧れの奈良へ行ったのは高校の修学旅行で、そのとき一番印象深かったのが、中宮寺の菩薩半跏像です。そこで受けた感動が、美術史という学問を志すきっかけになったのだと思います。
伊藤 中宮寺の菩薩半跏像のどういう部分に惹かれたのですか?
長岡 当時は高校生ですから、いまの研究姿勢とは全然違いますが、実際に目の前にした時、その形や色、佇まいの美しさに心を強く打たれました。仏像というより、一つの芸術作品として見ていたのでしょうね。修学旅行ではその後、京都へ行きました。その時に京都国立博物館でたまたま全米美術館収集世界名作展が開かれていて、そこで見たラファエロの『聖母子像』もなぜだかすごく記憶に残っています。私の中では、中宮寺の菩薩半跏像とラファエロの『聖母子像』が美術体験の始まりでした。
伊藤 なんだかおもしろい組み合わせですね。
長岡 おそらく当時の自分は、どちらもざっくりと「アート」と考えていたのだと思います。しかし大学生になって美術史を学ぶうち、ある時期から意識的に信仰や宗教的な意味あいに力点を置いて仏像を見るようになり、相対的に「アート的」な見方をしなくなっていったような気がします。
伊藤 それはどういうことでしょうか?
長岡 ちょっと難しい話になるかもしれませんが、1878(明治11)年にアメリカからフェノロサという美術史家が日本にやってきました。当時の日本は欧化政策の影響で日本古来の文化財が軽視されていた状況でしたが、フェノロサは仏像などを西洋のアート的な視点から高く評価し、文化財保護や美術教育に大きな功績を残した人物です。彼が仏像を評価した視点とは、仏像をご本尊として見るというよりは、ひとつの彫刻作品としての美しさに注目するものでした。
私が中宮寺で菩薩半跏像を見たのは、まさにそのアート的な視点からだったのだと思います。しかし、美術史を学んでいくうち、仏像というのはフェノロサのように、造形の美しさを評価するだけではなく、本来もっている信仰や宗教的な部分を抜きにしては語れないのではないかと考えるようになっていきました。
表現する「芸術家」と仏を信仰する「仏師」
伊藤 いまでは「アート」という言葉は一般的ですが、いろんな歴史や考え方があるのですね。
長岡 1873(明治6)年にドイツ語の“Schöne Kunst”(ファイン・アート)の翻訳語として生まれた言葉が「美術」です。逆に言えば、それ以前の日本にはアートという考え方はありませんでした。ですからアートは、近代的な西洋の考え方であると言えるでしょう。
伊藤 先生が専門にされている日本美術史という分野も、「美術」という言葉が入っていますね。
長岡 そうですね。「日本美術史」という学問も、明治に生まれたものです。そのなかでも、絵画・彫刻・工芸というジャンルに分類されていったのですが、とりわけ重要視されたのが彫刻です。なぜなら、日本美術史を考えていくうえでその基盤となる古代美術史は欠かせないわけですが、かつて多数存在していた日本の古代絵画は劣化によってそのほとんどが失われてしまっています。そうした事情から、仏像をはじめとした彫刻が日本美術史の主要なテーマとなりました。
伊藤 たしかに日本の古い彫刻作品といえば、やっぱり仏像が思い浮かびます。
長岡 そうですよね。一方で「西洋美術史」は、16世紀のルネサンス美術の登場とともに生まれたものです。ルネサンスというのは、レオナルド・ダヴィンチやミケランジェロ、ラファエロなどいわゆる「芸術家」が活躍した時代で、豊かな人間性が表現されていきました。それに対して、仏像の多くは作者不明です。そして作者の立場は、「芸術家」というよりも仏師などの「職人」ですから、自己表現の手段として仏像を制作したわけではない。その意味で、両者には大きな違いがあると言えるでしょう。
伊藤 さきほどお話に出たラファエロの『聖母子像』や、ミケランジェロの『最後の審判』などは、キリスト教を題材にした宗教美術という点では仏像とも共通していますが、作者という考え方に注目してみると違いがありますね。仏師のなかで有名な人物と言えば、東大寺の「金剛力士立像」を作った運慶と快慶でしょうか。
長岡 特に快慶は、自ら「巧匠」と名乗って、仏像の足の裏の「ほぞ」と呼ばれる突起部分に署名をしていました。通常は見えない場所ですが、自分の作品であるという証を残しているのです。ただ仏師というのは平安時代以降、職人のなかでも僧侶やそれに準じる身分を得て寺院の仏像制作所に属していて、快慶も熱心に阿弥陀仏を信仰していたと言われます。ですから残された署名は、自らを誇示するためではなく、一人の宗教者としての信仰心から為されたものだと私は思っています。
伊藤 仏像は仏師の自己表現ではないにせよ、そんなふうに一つひとつの仏像に込められた願いが、美しさとして現れているのかもしれませんね。
偶像と祈りの関係
伊藤 西洋で仏像に近い存在となると、どんなものがありますか?
長岡 ルネサンスよりもさらに遡った中世の時代のイコンではないでしょうか。イコンとは、ギリシャ語で「像」を意味する「エイコーン」が語源で、キリスト教において崇敬の対象とされる「聖像」のことです。キリストや聖母、またその生涯や聖書の一場面が描かれていることが多いですね。中世の教会にあるイコンの多くは、名もなき職人によって作られています。そして彼らは、おそらく敬虔な修道士であり、祈りを捧げながら像を作り上げていたのでしょう。
伊藤 イコンは、仏教でいうご本尊のような存在でしょうか。仏像と仏師の関係と似ている気がします。
長岡 仏像とお堂の関係性と同じように、イコンにとっても教会という場所が重要になってきます。例えば、12~15世紀に広まったゴシック建築のヴォールトと呼ばれる特徴的な天井様式は、天にまで昇るような奥行きを感じるものです。あるいはステンドグラスも、天からの光に満ちたような室内を演出します。つまり、祈りが神へと通じるような「祈りの空間」として教会がデザインされていると言えるでしょう。
そこで大切なのは、イコンという偶像の向こう側に神の存在があるということです。人物としてのイエス・キリストはもうこの世にいませんが、磔刑像などのイコンを通してキリストの生涯を追体験することで、キリストの救済への苦労を心にとどめるという目的が、キリスト教会の基本にはあります。祈りの空間である教会のなかで神と通じ合い、イコンが発するメッセージが祈りのなかで受け取られていくということが大切なのです。
伊藤 浄土真宗の場合、お寺やお内仏(仏壇)に安置されるご本尊は、「方便法身尊形」と呼ばれます。親鸞聖人は阿弥陀如来について「いろもなし、かたちもましまさず」、つまり本来は阿弥陀如来とは色も形もなく目で見ることができない存在であると言われます。ですから木像や絵像、そして「南無阿弥陀仏」と仏の名が書かれた名号本尊は、本来は色も形もない阿弥陀如来の真実のはたらき(法性法身)が、私たちの前に形となって姿を現わしている(方便法身)ということになります。
私たちがご本尊を前にお念仏するなかで、阿弥陀如来のはたらきにふれていく。こうした役割は、イコンと共通する部分がありますね。
長岡 『法然上人絵伝』に、仏像が多く登場する場面があります。法然上人の臨終が描かれた巻において、臨終の者たちの前に阿弥陀如来の木像や絵像が置かれる場面が繰り返し描かれているのですが、そこでは臨終に際して阿弥陀如来が来迎しているイメージをしっかり持つために、仏像や仏画をそばに置いているのです。
さらに法然の臨終の場面では、弟子たちが法然のために仏像を用意するのですが、法然は断り、阿弥陀如来はもう来られていると指を差して言っている場面が描かれています。浄土真宗の考え方とは違うかもしれませんが、この絵巻が描かれた時に仏像をどのようにとらえていたのかということが読み取れる非常に面白い資料だと思います。
見ることのできない仏像のもとへ参拝する理由
長岡 ところで伊藤さんがお住まいの滋賀県には、石山寺というお寺がありますね。紫式部が参籠し『源氏物語』の構想を練ったという伝承も残っていて、古くから多くの人がお参りに訪れたとても有名なお寺です。そこに安置されている石山観音は日本でも代表的な観音菩薩像で、安産・福徳・縁結などの利益をいただけるとして信仰を集めてきました。ただ、その観音菩薩は秘仏なんです。
伊藤 秘仏ということは、お参りに行っても姿を見ることはできないということですね。
長岡 ええ。平安時代の人たちは、都に近いこともあって頻繁に石山寺へお参りしていましたが、秘仏ですので石山観音の姿を見に行っていたわけではないのです。
ではなぜそんなにも頻繁に訪れていたのか。それを知る手がかりが『石山寺縁起絵巻』という絵巻にあります。そこには石山寺に参籠している人たちが描かれているのですが、多くの人が寝ているのです。
伊藤 せっかく行ったのに寝てしまうんですか!?(笑)
長岡 はい。一晩、あるいは一週間ほど参籠するのですが、その目的は石山観音から夢のお告げをいただくことです。そうした霊験が起こるのは、多くは夢の中、もしくは寝ているのか起きているのか分からない夢うつつの状態の時だと言われるので、みな寝ているのです。この場合、参拝者にとって仏像とは観賞するものではなかったということがはっきりと言えるでしょう。ある意味当たり前のことかもしれませんが、私もこうした事例にふれる中で、仏像を単に美術作品として考えていくわけにはいかないと思いました。
伊藤 参拝にこられる方は、仏像やその場所にそなわった霊験のようなものを求めてこられていたのですね。
長岡 そうです。仏像が作られる際には、その素材も厳選します。奈良県の長谷寺にある長谷観音は、比良山の方から流れ出てきた木で作られていると伝えられます。その木は不思議な力を持った霊木であり、それを仏師が願いを込めて像へと作りあげ、観音菩薩は「補陀落」という山におられるというお経の内容になぞらえて、長谷寺があるような高い山に安置する。そうした材料と作り手と場所に込められたものを追体験するために、後の人たちは頻繁に参拝されたのではないでしょうか。
伊藤 博物館で見ることのできる仏像は、そうした元の意味合いから切り離されてしまっているのかもしれませんね。
長岡 別の場所に移されてしまうと、そうした追体験はかないません。ただ現在は、住職がいなくなってしまった寺院などの寺宝が、盗難防止や管理のために博物館などに所蔵されるケースも多いです。
仏像だけど仏像じゃない「生身の釈迦像」
伊藤 私はイラストレーターとしてのお仕事もさせていただいているのですが、ずいぶん前に旅行雑誌から「癒やされツアー」と称して関西の仏像を巡ってイラストを描くというご依頼がありました。編集の方と一緒に車で4、5軒のお寺をまわったのですが、完成した誌面には「最近疲れ気味のイラストレーターがお寺を回って癒やされに行きます」というような文言が添えられていました(笑)。
長岡 企画の都合に合わせてそう書かれてしまったのですね(笑)。癒やしはありましたか?
伊藤 いえ、私は絵を描くのに必死で…。描いた中で印象に残っているのは、京都の清凉寺にある釈迦如来立像です。先生は清凉寺の研究もされているそうですが、この像は50年ほど前の調査の際、背中にフタのようなものがあることがわかって、そこから絹で作られた五臓六腑の模型が出てきたことで大きな話題になったそうですね。
長岡 はい。清凉寺のお釈迦さまは、「生身の釈迦像」と言われています。「生身」は仏教語で、本来仏像に使う言葉ではありません。生身とはこの世にいらっしゃる仏さま、それに対して「法身」は本質としての目に見えない仏さまだと捉えています。仏像研究において「生身」という言葉は、鎌倉時代以降は非常に重要なキーワードになります。
仏教本来の考え方としては、仏像はあくまでも偶像なので、仏さまではありません。ですから清凉寺の釈迦像も、お釈迦さまそのものではありません。ところが清凉寺の釈迦像は、10世紀に日本に中国から伝来したもので、さきほどおっしゃられた五臓六腑が入っていました。それはつまり、生きているお釈迦さまに見立てて作られているということです。仏像だけど、仏像じゃないという意味で生身と言われます。
伊藤 たしかに内臓を像の中に入れるというのはリアルの追求というより、より生きている姿に近づけたいという思いを感じます。
長岡 お釈迦さまは、2500年以上前にお亡くなりになった人物です。その方にお会いしたいという思いで生まれてきたのが仏像であり、いかに仏像を仏に近づけるかという工夫が仏像を造る上での重要な点になりました。そうした強い思いのなかから、このように特殊な仏像も生まれてきたのだと思います。
仏教における造形の役割とは
伊藤 おなじ仏像でも本当に様々ですね。真宗のお寺にお参りさせてもらう機会は多いですが、同じ宗派の阿弥陀さまでもやっぱりお顔はちょっとずつ違うなと感じます。阿弥陀さまは男でも女でもないと思いますが、私がお預かりしているお寺によく来られる方は、「ここのお寺のは男前やな」とか、「ハンサムやな」とかおっしゃる方もいます。
長岡 さっきも話に出ましたが、仏教では方便という考えがありますよね。お釈迦さまは、救済を求めている者それぞれにふさわしいような形で教えを説かれます。ですから、求めている人が違うからお顔も違って見えてくる。そんなふうに説明することができるかもしれません。
清凉寺の釈迦もそうですが、生身の釈迦といってもやはり、法身という目に見えない真理を本質として、目に見える形であらわされた仏像であるという点は変わりません。その考え方のなかで五臓六腑を入れるなど、様々な表現の工夫がなされていきました。
ほかにも釈尊の遺骨である仏舎利や、結縁交名と呼ばれる文書が仏像に納められていることがあります。結縁交名とは、仏像に縁をつないだ人たちの名前を書き入れた文書で、多くの人から少しずつお金を集めて仏像を作るのですけど、おそらく仏像を尊いものにするためには多くの人が縁を結んだ方が良いと考えられていて、一万を超えるような名前が入ったものもあります。
伊藤 それはすごい数です。一つの仏像にそれだけの人の思いが込められているということですね。
長岡 その通りですね。仏教における造形の一番の役割は、見えないものを見えるようにするということです。それは簡単なことではなく、多くの人の思いのなかで成立してきたものなのでしょう。
阿弥陀信仰に関して言えば、阿弥陀如来の世界である浄土が盛んに描かれてきました。例えば、奈良の法華寺にあった阿弥陀浄土院という庭園は、浄土の世界が再現されており、光明皇后が亡くなるときに浄土往生を願って作られたものです。また京都の平等院鳳凰堂も、藤原頼通の浄土往生を願って作られました。つまりこれらは、浄土の世界を寺や庭園にしてしまうことで、目に見えない浄土をできるだけ身近に感じる手立てとされてきたわけです。宗派や教義、表現の方法はさまざまですが、仏教を求める人々の思いが、仏教美術という歴史に現れているのではないでしょうか。
仏像に会うのは一つの物語
伊藤 今日のお話をお聞きして、また新たな視点で仏像を見てみたいなと思いました。今後、仏像を見る際のアドバイスをお聞きしたいです。
長岡 仏像そのものを見るチャンスは、展覧会なども含めたくさんあると思います。スポットライトを浴びて隅々まで見える仏像を鑑賞する機会を私は否定しません。それも大事なことだと思います。
しかし、仏像に会うのは一つの物語です。山門を入って、長い階段を上がって行って、お堂の中に入っていく。やはりそうしたプロセスを大事にすることで、仏像が作られた当時の人の気持ちに少しだけ近づくことができるのではないかと思います。なぜこの場所に、こんなに立派な仏像があるのか。その来歴が感じられるかもしれません。仏像に会う物語を大事にされたらいいのではないかと私は思います。
伊藤 いまその言葉をお聞きして、私がお預かりするお寺の本堂にも物語があるんだなということを思わせていただきました。うちのご本尊は550年前からいらっしゃると聞いています。それだけ長い間、私たちを見てきてくださっているんだなと思うと、身の引きしまるような思いがします。多くの人が手を合わせて、教えが伝えられてきたという歴史を感じますね。
子どもの頃からご本尊の前をむやみに横切ってはだめだよと親から言われていました。いまは僧侶として出仕してお勤めしますが、本堂の荘厳は浄土を表現したものです。ですから私も私という個人ではなく、浄土世界の荘厳の一つとして出仕させていただいています。今日お話しさせていただいて、衣を身につけて荘厳の一つとして出仕する僧侶というのは、とても近くで仏さまの教えを聞かせてもらっているのだなと改めて思いました。
長岡 本堂に出仕される僧侶も荘厳の一部だと考えるのですね。とても興味深いお話です。浄土真宗の寺院は浄土世界をどのように表現して、人々はどのようにそこにふれてきたのか。そうしたことについても改めて勉強してみたいなと思います。今日はいろいろお聞きできて楽しかったです。ありがとうございました。
伊藤 こちらこそありがとうございました。
長岡龍作 ながおか りゅうさく
1960年生まれ。青森に生まれ北海道で育つ。東北大学大学院教授。専門は日本彫刻史、仏教美術史。著書に『仏像―祈りと風景』(敬文舎)、『仏教と造形―信仰から考える美術史―』(中央公論美術出版)、編著に『講座日本美術史 第4巻 造形の場』(東京大学出版会)、『仏教美術論集5 機能論―つくる・つかう・つたえる』(竹林舎)など多数。
伊藤真希 いとう まき
1970年滋賀県生まれ。真宗大谷派蓮池山真願寺住職。東本願寺同朋会館嘱託補導。イラストレーター、消しゴムはんこ作家。月刊誌『同朋』2021年1月号〜2022年12月号の表紙イラスト担当。『makihanco』として消しゴムはんこ講師やはんこ制作を行う。共著に『たのしさいっぱい!消しゴムはんこの図案集』『和の消しゴムはんこ図案集』(ともにブティック社)ほか。
教えを求める人々の思いが、仏教美術の歴史に現れている。
日本美術史の重要なテーマの一つでもある仏像。そこからから見えてくるアートと信仰の関係性とは。
日本美術史の視点から仏像を研究し続けてきた長岡龍作さんと、
イラストレーターや消しゴムはんこ作家としても活躍する伊藤真希さんの対談です。
家族旅行はいつも奈良のお寺
伊藤 私は滋賀県長浜市の寺に生まれ、昨年から住職を務めています。琵琶湖の湖北にあたる場所で、真宗大国といわれるほど浄土真宗のお寺が多い場所です。また、消しゴムはんこ作家としても活動しておりまして、この月刊誌『同朋』では昨年まで表紙を担当させてもらいました。門徒さんに向けて、仏さまをモチーフにした作品を作ったこともあり、このたびは仏像のお話などをお聞きしたいと楽しみにして参りました。よろしくお願いいたします。
長岡 こちらこそよろしくお願いします。伊藤さんがお住まいの地域は、真宗寺院も多いですが、歴史ある観音菩薩像が安置されてる寺院もたくさんありますね。
伊藤 はい。近年は「観音の里」と呼ばれて、全国各地から多くの方々が参拝に訪れています。ただ、私にとっての仏像との出会いというと、やはり生まれたお寺の本堂に安置されている阿弥陀如来像です。生まれてからずっと、手を合わせてきた、共に暮らしてきたという感覚です。
前住職の父は高校で日本史の先生をしていたこともあってか、仏像に大変関心を持っていたので、家族旅行というと、必ずといっていいほど奈良のお寺でした。いろんなお寺の廊下や山門で撮った家族写真がたくさん残っています。いま思えば貴重な経験だったかもしれませんが、正直なところまだ幼なかった当時の私にとっては全然面白くありませんでした(笑)。それでも記憶に残っているのは、母が「この優しい顔はどう思う?」とか「しなやかな体がきれいやね」と、仏さまの姿やお顔について、子どもにもわかりやすいように話をしてくれたことですね。
今回、先生のご著書『日本の仏像』(中公新書)を読ませていただいたのですが、紹介されているお寺にあの頃お参りしていたなと懐かしく思い返しつつも、それぞれの仏像の願いや背景を知って、改めてお参りしてみたいなと思いました。
長岡 お読みいただきありがとうございます。私は、子ども時代は北海道で育ちました。私の地元も真宗寺院がたくさんある地域ですが、古い仏像はありませんでしたので、関西の古い寺院や仏像に、遠い土地から憧れるような仏像少年でした。
フェノロサから始まった仏像の「アート的」な見方
長岡 初めて憧れの奈良へ行ったのは高校の修学旅行で、そのとき一番印象深かったのが、中宮寺の菩薩半跏像です。そこで受けた感動が、美術史という学問を志すきっかけになったのだと思います。
伊藤 中宮寺の菩薩半跏像のどういう部分に惹かれたのですか?
長岡 当時は高校生ですから、いまの研究姿勢とは全然違いますが、実際に目の前にした時、その形や色、佇まいの美しさに心を強く打たれました。仏像というより、一つの芸術作品として見ていたのでしょうね。修学旅行ではその後、京都へ行きました。その時に京都国立博物館でたまたま全米美術館収集世界名作展が開かれていて、そこで見たラファエロの『聖母子像』もなぜだかすごく記憶に残っています。私の中では、中宮寺の菩薩半跏像とラファエロの『聖母子像』が美術体験の始まりでした。
伊藤 なんだかおもしろい組み合わせですね。
長岡 おそらく当時の自分は、どちらもざっくりと「アート」と考えていたのだと思います。しかし大学生になって美術史を学ぶうち、ある時期から意識的に信仰や宗教的な意味あいに力点を置いて仏像を見るようになり、相対的に「アート的」な見方をしなくなっていったような気がします。
伊藤 それはどういうことでしょうか?
長岡 ちょっと難しい話になるかもしれませんが、1878(明治11)年にアメリカからフェノロサという美術史家が日本にやってきました。当時の日本は欧化政策の影響で日本古来の文化財が軽視されていた状況でしたが、フェノロサは仏像などを西洋のアート的な視点から高く評価し、文化財保護や美術教育に大きな功績を残した人物です。彼が仏像を評価した視点とは、仏像をご本尊として見るというよりは、ひとつの彫刻作品としての美しさに注目するものでした。
私が中宮寺で菩薩半跏像を見たのは、まさにそのアート的な視点からだったのだと思います。しかし、美術史を学んでいくうち、仏像というのはフェノロサのように、造形の美しさを評価するだけではなく、本来もっている信仰や宗教的な部分を抜きにしては語れないのではないかと考えるようになっていきました。
表現する「芸術家」と仏を信仰する「仏師」
伊藤 いまでは「アート」という言葉は一般的ですが、いろんな歴史や考え方があるのですね。
長岡 1873(明治6)年にドイツ語の“Schöne Kunst”(ファイン・アート)の翻訳語として生まれた言葉が「美術」です。逆に言えば、それ以前の日本にはアートという考え方はありませんでした。ですからアートは、近代的な西洋の考え方であると言えるでしょう。
伊藤 先生が専門にされている日本美術史という分野も、「美術」という言葉が入っていますね。
長岡 そうですね。「日本美術史」という学問も、明治に生まれたものです。そのなかでも、絵画・彫刻・工芸というジャンルに分類されていったのですが、とりわけ重要視されたのが彫刻です。なぜなら、日本美術史を考えていくうえでその基盤となる古代美術史は欠かせないわけですが、かつて多数存在していた日本の古代絵画は劣化によってそのほとんどが失われてしまっています。そうした事情から、仏像をはじめとした彫刻が日本美術史の主要なテーマとなりました。
伊藤 たしかに日本の古い彫刻作品といえば、やっぱり仏像が思い浮かびます。
長岡 そうですよね。一方で「西洋美術史」は、16世紀のルネサンス美術の登場とともに生まれたものです。ルネサンスというのは、レオナルド・ダヴィンチやミケランジェロ、ラファエロなどいわゆる「芸術家」が活躍した時代で、豊かな人間性が表現されていきました。それに対して、仏像の多くは作者不明です。そして作者の立場は、「芸術家」というよりも仏師などの「職人」ですから、自己表現の手段として仏像を制作したわけではない。その意味で、両者には大きな違いがあると言えるでしょう。
伊藤 さきほどお話に出たラファエロの『聖母子像』や、ミケランジェロの『最後の審判』などは、キリスト教を題材にした宗教美術という点では仏像とも共通していますが、作者という考え方に注目してみると違いがありますね。仏師のなかで有名な人物と言えば、東大寺の「金剛力士立像」を作った運慶と快慶でしょうか。
長岡 特に快慶は、自ら「巧匠」と名乗って、仏像の足の裏の「ほぞ」と呼ばれる突起部分に署名をしていました。通常は見えない場所ですが、自分の作品であるという証を残しているのです。ただ仏師というのは平安時代以降、職人のなかでも僧侶やそれに準じる身分を得て寺院の仏像制作所に属していて、快慶も熱心に阿弥陀仏を信仰していたと言われます。ですから残された署名は、自らを誇示するためではなく、一人の宗教者としての信仰心から為されたものだと私は思っています。
伊藤 仏像は仏師の自己表現ではないにせよ、そんなふうに一つひとつの仏像に込められた願いが、美しさとして現れているのかもしれませんね。
偶像と祈りの関係
伊藤 西洋で仏像に近い存在となると、どんなものがありますか?
長岡 ルネサンスよりもさらに遡った中世の時代のイコンではないでしょうか。イコンとは、ギリシャ語で「像」を意味する「エイコーン」が語源で、キリスト教において崇敬の対象とされる「聖像」のことです。キリストや聖母、またその生涯や聖書の一場面が描かれていることが多いですね。中世の教会にあるイコンの多くは、名もなき職人によって作られています。そして彼らは、おそらく敬虔な修道士であり、祈りを捧げながら像を作り上げていたのでしょう。
伊藤 イコンは、仏教でいうご本尊のような存在でしょうか。仏像と仏師の関係と似ている気がします。
長岡 仏像とお堂の関係性と同じように、イコンにとっても教会という場所が重要になってきます。例えば、12~15世紀に広まったゴシック建築のヴォールトと呼ばれる特徴的な天井様式は、天にまで昇るような奥行きを感じるものです。あるいはステンドグラスも、天からの光に満ちたような室内を演出します。つまり、祈りが神へと通じるような「祈りの空間」として教会がデザインされていると言えるでしょう。
そこで大切なのは、イコンという偶像の向こう側に神の存在があるということです。人物としてのイエス・キリストはもうこの世にいませんが、磔刑像などのイコンを通してキリストの生涯を追体験することで、キリストの救済への苦労を心にとどめるという目的が、キリスト教会の基本にはあります。祈りの空間である教会のなかで神と通じ合い、イコンが発するメッセージが祈りのなかで受け取られていくということが大切なのです。
伊藤 浄土真宗の場合、お寺やお内仏(仏壇)に安置されるご本尊は、「方便法身尊形」と呼ばれます。親鸞聖人は阿弥陀如来について「いろもなし、かたちもましまさず」、つまり本来は阿弥陀如来とは色も形もなく目で見ることができない存在であると言われます。ですから木像や絵像、そして「南無阿弥陀仏」と仏の名が書かれた名号本尊は、本来は色も形もない阿弥陀如来の真実のはたらき(法性法身)が、私たちの前に形となって姿を現わしている(方便法身)ということになります。
私たちがご本尊を前にお念仏するなかで、阿弥陀如来のはたらきにふれていく。こうした役割は、イコンと共通する部分がありますね。
長岡 『法然上人絵伝』に、仏像が多く登場する場面があります。法然上人の臨終が描かれた巻において、臨終の者たちの前に阿弥陀如来の木像や絵像が置かれる場面が繰り返し描かれているのですが、そこでは臨終に際して阿弥陀如来が来迎しているイメージをしっかり持つために、仏像や仏画をそばに置いているのです。
さらに法然の臨終の場面では、弟子たちが法然のために仏像を用意するのですが、法然は断り、阿弥陀如来はもう来られていると指を差して言っている場面が描かれています。浄土真宗の考え方とは違うかもしれませんが、この絵巻が描かれた時に仏像をどのようにとらえていたのかということが読み取れる非常に面白い資料だと思います。
見ることのできない仏像のもとへ参拝する理由
長岡 ところで伊藤さんがお住まいの滋賀県には、石山寺というお寺がありますね。紫式部が参籠し『源氏物語』の構想を練ったという伝承も残っていて、古くから多くの人がお参りに訪れたとても有名なお寺です。そこに安置されている石山観音は日本でも代表的な観音菩薩像で、安産・福徳・縁結などの利益をいただけるとして信仰を集めてきました。ただ、その観音菩薩は秘仏なんです。
伊藤 秘仏ということは、お参りに行っても姿を見ることはできないということですね。
長岡 ええ。平安時代の人たちは、都に近いこともあって頻繁に石山寺へお参りしていましたが、秘仏ですので石山観音の姿を見に行っていたわけではないのです。
ではなぜそんなにも頻繁に訪れていたのか。それを知る手がかりが『石山寺縁起絵巻』という絵巻にあります。そこには石山寺に参籠している人たちが描かれているのですが、多くの人が寝ているのです。
伊藤 せっかく行ったのに寝てしまうんですか!?(笑)
長岡 はい。一晩、あるいは一週間ほど参籠するのですが、その目的は石山観音から夢のお告げをいただくことです。そうした霊験が起こるのは、多くは夢の中、もしくは寝ているのか起きているのか分からない夢うつつの状態の時だと言われるので、みな寝ているのです。この場合、参拝者にとって仏像とは観賞するものではなかったということがはっきりと言えるでしょう。ある意味当たり前のことかもしれませんが、私もこうした事例にふれる中で、仏像を単に美術作品として考えていくわけにはいかないと思いました。
伊藤 参拝にこられる方は、仏像やその場所にそなわった霊験のようなものを求めてこられていたのですね。
長岡 そうです。仏像が作られる際には、その素材も厳選します。奈良県の長谷寺にある長谷観音は、比良山の方から流れ出てきた木で作られていると伝えられます。その木は不思議な力を持った霊木であり、それを仏師が願いを込めて像へと作りあげ、観音菩薩は「補陀落」という山におられるというお経の内容になぞらえて、長谷寺があるような高い山に安置する。そうした材料と作り手と場所に込められたものを追体験するために、後の人たちは頻繁に参拝されたのではないでしょうか。
伊藤 博物館で見ることのできる仏像は、そうした元の意味合いから切り離されてしまっているのかもしれませんね。
長岡 別の場所に移されてしまうと、そうした追体験はかないません。ただ現在は、住職がいなくなってしまった寺院などの寺宝が、盗難防止や管理のために博物館などに所蔵されるケースも多いです。
仏像だけど仏像じゃない「生身の釈迦像」
伊藤 私はイラストレーターとしてのお仕事もさせていただいているのですが、ずいぶん前に旅行雑誌から「癒やされツアー」と称して関西の仏像を巡ってイラストを描くというご依頼がありました。編集の方と一緒に車で4、5軒のお寺をまわったのですが、完成した誌面には「最近疲れ気味のイラストレーターがお寺を回って癒やされに行きます」というような文言が添えられていました(笑)。
長岡 企画の都合に合わせてそう書かれてしまったのですね(笑)。癒やしはありましたか?
伊藤 いえ、私は絵を描くのに必死で…。描いた中で印象に残っているのは、京都の清凉寺にある釈迦如来立像です。先生は清凉寺の研究もされているそうですが、この像は50年ほど前の調査の際、背中にフタのようなものがあることがわかって、そこから絹で作られた五臓六腑の模型が出てきたことで大きな話題になったそうですね。
長岡 はい。清凉寺のお釈迦さまは、「生身の釈迦像」と言われています。「生身」は仏教語で、本来仏像に使う言葉ではありません。生身とはこの世にいらっしゃる仏さま、それに対して「法身」は本質としての目に見えない仏さまだと捉えています。仏像研究において「生身」という言葉は、鎌倉時代以降は非常に重要なキーワードになります。
仏教本来の考え方としては、仏像はあくまでも偶像なので、仏さまではありません。ですから清凉寺の釈迦像も、お釈迦さまそのものではありません。ところが清凉寺の釈迦像は、10世紀に日本に中国から伝来したもので、さきほどおっしゃられた五臓六腑が入っていました。それはつまり、生きているお釈迦さまに見立てて作られているということです。仏像だけど、仏像じゃないという意味で生身と言われます。
伊藤 たしかに内臓を像の中に入れるというのはリアルの追求というより、より生きている姿に近づけたいという思いを感じます。
長岡 お釈迦さまは、2500年以上前にお亡くなりになった人物です。その方にお会いしたいという思いで生まれてきたのが仏像であり、いかに仏像を仏に近づけるかという工夫が仏像を造る上での重要な点になりました。そうした強い思いのなかから、このように特殊な仏像も生まれてきたのだと思います。
仏教における造形の役割とは
伊藤 おなじ仏像でも本当に様々ですね。真宗のお寺にお参りさせてもらう機会は多いですが、同じ宗派の阿弥陀さまでもやっぱりお顔はちょっとずつ違うなと感じます。阿弥陀さまは男でも女でもないと思いますが、私がお預かりしているお寺によく来られる方は、「ここのお寺のは男前やな」とか、「ハンサムやな」とかおっしゃる方もいます。
長岡 さっきも話に出ましたが、仏教では方便という考えがありますよね。お釈迦さまは、救済を求めている者それぞれにふさわしいような形で教えを説かれます。ですから、求めている人が違うからお顔も違って見えてくる。そんなふうに説明することができるかもしれません。
清凉寺の釈迦もそうですが、生身の釈迦といってもやはり、法身という目に見えない真理を本質として、目に見える形であらわされた仏像であるという点は変わりません。その考え方のなかで五臓六腑を入れるなど、様々な表現の工夫がなされていきました。
ほかにも釈尊の遺骨である仏舎利や、結縁交名と呼ばれる文書が仏像に納められていることがあります。結縁交名とは、仏像に縁をつないだ人たちの名前を書き入れた文書で、多くの人から少しずつお金を集めて仏像を作るのですけど、おそらく仏像を尊いものにするためには多くの人が縁を結んだ方が良いと考えられていて、一万を超えるような名前が入ったものもあります。
伊藤 それはすごい数です。一つの仏像にそれだけの人の思いが込められているということですね。
長岡 その通りですね。仏教における造形の一番の役割は、見えないものを見えるようにするということです。それは簡単なことではなく、多くの人の思いのなかで成立してきたものなのでしょう。
阿弥陀信仰に関して言えば、阿弥陀如来の世界である浄土が盛んに描かれてきました。例えば、奈良の法華寺にあった阿弥陀浄土院という庭園は、浄土の世界が再現されており、光明皇后が亡くなるときに浄土往生を願って作られたものです。また京都の平等院鳳凰堂も、藤原頼通の浄土往生を願って作られました。つまりこれらは、浄土の世界を寺や庭園にしてしまうことで、目に見えない浄土をできるだけ身近に感じる手立てとされてきたわけです。宗派や教義、表現の方法はさまざまですが、仏教を求める人々の思いが、仏教美術という歴史に現れているのではないでしょうか。
仏像に会うのは一つの物語
伊藤 今日のお話をお聞きして、また新たな視点で仏像を見てみたいなと思いました。今後、仏像を見る際のアドバイスをお聞きしたいです。
長岡 仏像そのものを見るチャンスは、展覧会なども含めたくさんあると思います。スポットライトを浴びて隅々まで見える仏像を鑑賞する機会を私は否定しません。それも大事なことだと思います。
しかし、仏像に会うのは一つの物語です。山門を入って、長い階段を上がって行って、お堂の中に入っていく。やはりそうしたプロセスを大事にすることで、仏像が作られた当時の人の気持ちに少しだけ近づくことができるのではないかと思います。なぜこの場所に、こんなに立派な仏像があるのか。その来歴が感じられるかもしれません。仏像に会う物語を大事にされたらいいのではないかと私は思います。
伊藤 いまその言葉をお聞きして、私がお預かりするお寺の本堂にも物語があるんだなということを思わせていただきました。うちのご本尊は550年前からいらっしゃると聞いています。それだけ長い間、私たちを見てきてくださっているんだなと思うと、身の引きしまるような思いがします。多くの人が手を合わせて、教えが伝えられてきたという歴史を感じますね。
子どもの頃からご本尊の前をむやみに横切ってはだめだよと親から言われていました。いまは僧侶として出仕してお勤めしますが、本堂の荘厳は浄土を表現したものです。ですから私も私という個人ではなく、浄土世界の荘厳の一つとして出仕させていただいています。今日お話しさせていただいて、衣を身につけて荘厳の一つとして出仕する僧侶というのは、とても近くで仏さまの教えを聞かせてもらっているのだなと改めて思いました。
長岡 本堂に出仕される僧侶も荘厳の一部だと考えるのですね。とても興味深いお話です。浄土真宗の寺院は浄土世界をどのように表現して、人々はどのようにそこにふれてきたのか。そうしたことについても改めて勉強してみたいなと思います。今日はいろいろお聞きできて楽しかったです。ありがとうございました。
伊藤 こちらこそありがとうございました。
長岡龍作 ながおか りゅうさく
1960年生まれ。青森に生まれ北海道で育つ。東北大学大学院教授。専門は日本彫刻史、仏教美術史。著書に『仏像―祈りと風景』(敬文舎)、『仏教と造形―信仰から考える美術史―』(中央公論美術出版)、編著に『講座日本美術史 第4巻 造形の場』(東京大学出版会)、『仏教美術論集5 機能論―つくる・つかう・つたえる』(竹林舎)など多数。
伊藤真希 いとう まき
1970年滋賀県生まれ。真宗大谷派蓮池山真願寺住職。東本願寺同朋会館嘱託補導。イラストレーター、消しゴムはんこ作家。月刊誌『同朋』2021年1月号〜2022年12月号の表紙イラスト担当。『makihanco』として消しゴムはんこ講師やはんこ制作を行う。共著に『たのしさいっぱい!消しゴムはんこの図案集』『和の消しゴムはんこ図案集』(ともにブティック社)ほか。